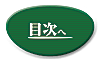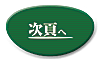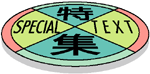 ロボットが人間に近づくために
ロボットが人間に近づくために

| |
矢野 雅文=文
text by Masafumi Yano
|
古来、人間は動物を直接利用するだけではなく、それに代わる機械をいかにして造るかという努力をしてきました。その結果、牛馬の労役に代わるガソリンエンジンなどの内燃機関は、生物一個体よりもはるかに大きな動力を実現しました。また、人間の作業を肩代わりするロボットは、その頭脳であるコンピュータが、大量のデータを人間よりけた違いの速さで処理することができます。それでは機械は人間を超えたと言えるのでしょうか?
エネルギー効率70%の夢
生物の運動をつかさどるのは、筋肉のアクトミオシンに代表されるモータータンパク質で構成された、分子的装置のエンジンです。筋肉の出力は断面積に比例し、収縮速度は筋肉の長さに比例します。このエンジンは、1円玉の断面積で最大約10kg の力が出ます。この単位体積当たりの出力は現在のどんなモータにも出せないものです。さらに、その特長はそのエネルギー変換効率にあります。
内燃機関は、高熱源と低熱源という温度差のある二つの系間で初めて作動します。エネルギー変換効率はこの温度によって決まりますので、通常はせいぜい40%程度です。これに対して、カメの筋肉では、エネルギー変換効率は70%にも上ると言われています。筋肉は均一温度で仕事ができるわけですから、通常の内燃機関と作動原理が異なります。
写真2は、世界で初めて作った生体エンジンです。筋肉から取り出した蛋白質を人工的に筋肉のように配列させると、羽根車が化学エネルギーを力学エネルギーに変換しながら回ります。このような再構成した生体エンジンを詳細に調べることで、非常に高いエネルギー変換効率で動く機構が分かりました。
内燃機関は、燃焼することによって化学エネルギーをいったんランダムな熱エネルギーに変換するために、変換効率が落ちます。生体エンジンは、分子が連結した規則正しい配列をしているので、ランダムな方向に分子は動くことができません。そのため、化学エネルギーが熱エネルギーに変換されることなく、直接、力学エネルギーに変換することができます。構造的な制約のために一個の分子の動きが他の分子に伝わり、その動きの影響を受けながら別の分子が力を発生するという、動的な協力性が存在することが高い効率の秘密です。
筋肉を構成する分子は、高いエネルギーの寿命の長い反応中間体が力を出すのだと分かっており、全体の力は力を出している分子の中間体の数に比例します。
一方、化学反応速度はこの中間体のエネルギー変換の速度によって決まります。この場合、エネルギー変換速度は分子の出す力と動く速度の積に比例しますが、力は分子間力ですから一定とみなしますと、化学反応速度はこの分子の動く速度によって決まります。荷重が大きい場合は力を出す中間体の数が増えて、荷重を少しだけ上回る力が出た時に収縮します。また、荷重が小さい場合は速度が速くなり力を出す中間体の数が減少し、荷重と力が釣り合ったところで収縮します。使われたエネルギーに等しい分だけが、化学反応によって供給されることになりますので、効率よくエネルギーを変換することになります。
このように生体システムでは、制御系と力の発生が一体となっているので、自律的にシステムを制御できることが大きな特長です。
この生体エンジンは蛋白質で作られていますので、寿命が限られています。蛋白質に代わる丈夫な物質で作ることが可能になれば、精密な動きをするコンパクトなエンジンが可能になります。将来は、体内に埋め込むことのできる、人工の心臓なども可能になるかも知れません。
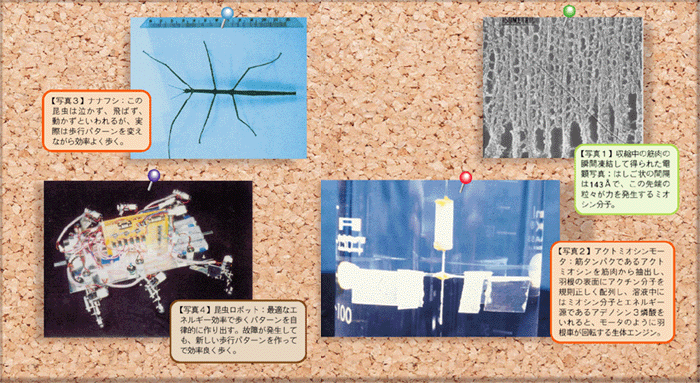
複雑な環境下で自在に動く
生物個体レベルでの運動も、環境変化に応じて柔軟に対応することができます。馬などの4つ足動物は、速度に応じて、ウォーク、トロット、ペース、ギャロップと、歩くパターンが変化します。写真3のような昆虫でも、速度に依存して歩行パターンが変化します。また、動物は脚が故障しても、残りの脚を使って新しいパターンで歩くことができます。この時、動物の消費するエネルギーは、歩行速度に依存しないで距離に比例します。
このパターン変化は、筋肉のエネルギー変換効率と関係していて、各脚がなるべく高い効率のところで働けるように中枢神経系が情報を処理し、最適なエネルギー効率で歩ける制御情報を生成するからだということが分かりました。
環境変化やどこに故障が起きるかは予測できないので、動物はすべての場合に対して最適なパターンをあらかじめ用意しておくことはできません。したがって、動物は状況に合わせて自律的に情報を作る必要があるわけです。実際、動物は、これが可能になるような「情報生成ルール」を持っており、実環境下での運動に大変有効な方法になっています。
このしくみを備えたロボットの例が、写真4の6本脚の昆虫ロボットです。このロボットに目的地と歩行の目標速度を与えますと、動かす環境が変わっても脚が故障しても、エネルギー効率を最適化しながら目標速度を保って最適な軌道で目的地に到達します。環境が変わったり、脚が故障したときにどのようにするのかという情報を与えていませんので、このロボットは必要な情報を作っていることになり、生物の運動に一歩近づいたことになります。
柔軟な認識システムに向けて
これだけでは、まだ生物の能力には遠く及びません。それは環境を認識したり、予測する能力が、生物に比べて圧倒的に低いからです。
人工知能が認識するシステムとして期待された時もありました。が、これまでの人工知能は人間があらかじめ教えた情報しか処理できませんので、複雑な環境にはとても太刀打ちできません。認識するための情報が足りないわけですから、認識するための情報を生成する必要があります。
新しい認識システムの研究はまだ始まったばかりですが、これが可能になれば、ロボットは人間に限りなく近づくことになります。複雑な実環境に対して柔軟に対応できる夢のシステムは、21世紀には大いなる研究の進展が期待されます。
 やのまさふみ
やのまさふみ
1946 年生まれ
現職:東北大学電気通信研究所教授
専門:生体システム工学

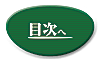
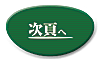
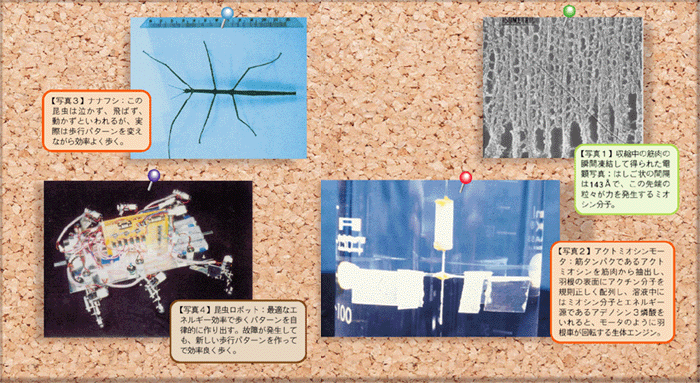
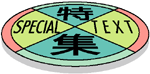 ロボットが人間に近づくために
ロボットが人間に近づくために
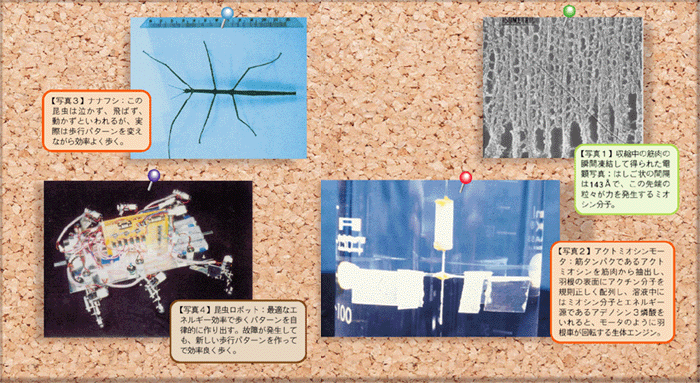
 やのまさふみ
やのまさふみ