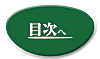走査型トンネル顕微鏡
いまから20年余り前、それまでの顕微鏡とはまったく動作原理を異にする新しい顕微鏡が発明されました。その最大の特長の1つは従来にない高い倍率にありました。固体表面の1つ1つの原子を区別して画像化する(“観る”)ことができ、当時難問とされていたいくつかの固体表面の原子配列をたちどころに決定してみせました。それが走査型トンネル電子顕微鏡(STM)です。
STMでは探針と呼ばれる鋭く尖った針を試料面から1nm(nmはナノメートル。mmの100万分の1に相当する長さの単位)程度の距離まで近づけます。このとき、試料表面と探針先端の間のギャップを電子トンネル効果による電流が流れます。一定のトンネル電流が流れるようにギャップ間隔を調節しながら表面をなぞって、表面凹凸の地図を描いたものがSTM像です。
STMはその後の表面物性の研究に一大革命をもたらしました。しかし、発明当時から認識されており、まだ解決されていない重要な問題が残っています。それは、STM像で見える原子レベルの極微細構造(ナノ構造)が何でできているか、どのような性質を持っているか、まではわからないということです。
例えば、図の(a)は銅の単結晶表面に一酸化炭素を隙間なく一層だけ敷き詰めた表面(Cu(110)‐(2 1)CO)のSTM像、(b)はその輪郭像です。描画範囲は横10nm、縦8.5nmです。ステップと呼ばれる銅原子1個分の高さを有する段差で区切られた平坦な部分(テラス)に原子サイズ(直径約1nm)の突起がみられます。サイズから判断してこの突起は単一の原子もしくは分子には違いないのですが、具体的に何であるのかをこの像から判断することはできません。
 |
STM発光分光
STMの発明から数年後、探針―試料間のギャップから可視光が出ていることが発見されました。この光は、STM探針の先から注入された電子のエネルギーによって試料中の電子が励起され、励起された電子が元の状態に戻るときに出てくることがわかっています。
図の突起のように、周りと異なる原子もしくは分子が存在する地点では、電子が元の状態に戻るときの「戻り方」が周囲と異なるので、違った色の可視光を出すようになります。この発光を解析すると(STM発光分光)、図の突起は原子酸素であると同定されます。このような原子1個1個の精度で表面に吸着したものを同定できる方法は他にはありません。
ナノテクノロジーへの応用
ナノテクノロジーは、個々の分子やナノ結晶のような、ナノサイズの物質に特有にみられる特性や現象を応用する技術分野です。STM発光分光はこの分野における極めて有効な評価手法となります。
例えば、STMの進歩により、まるで箸で原子や分子をつかむように、探針で固体表面に並べた原子や分子を移動させることができるようになってきました。さらに、探針の先端からの電子注入により、特定の一つの分子だけに化学反応を起こすこともできます。このような手法を使うと、まるで積み木を組み合わせるように、原子1つひとつ、分子1つひとつを組み立ててゆき、従来にない高い機能、新しい機能を有する人工ナノ構造が創製できると期待され、現在活発に研究されています。
この場合、原料となる原子・分子の同定、化学反応生成物の判定、創製されたナノ構造の物性評価などが重要であることは言うまでもありません。このような目的にSTM発光分光は極めて有効な手法であると言えます。