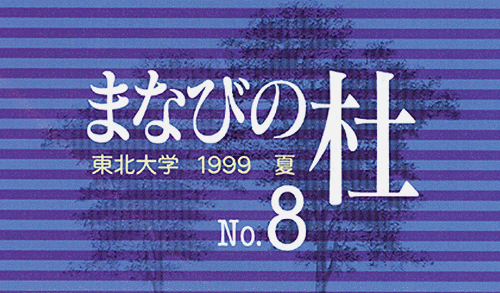

−化石シリーズ 第2回−
「四放サンゴ」
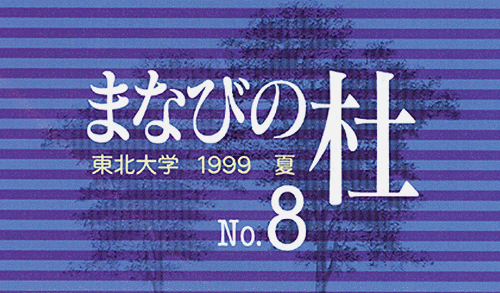

サンゴ(珊瑚)といえば、指輪、ネクタイピン、ネックレスなどに加工されているアカサンゴ、モモイロサンゴなどの宝石サンゴを思い浮かべる人が多いかもしれません。しかし、サンゴには、宝石サンゴ以外にも、さまざまな種類があります。南の島々のサンゴ礁を彩るミドリイシ、ハマサンゴなどの六放サンゴやアオサンゴ、クダサンゴ、ヒドロサンゴなどは、今生きているサンゴの主なものですが、太古のサンゴ礁にも種類の全く異なるサンゴが繁栄していました。
ここに紹介するサンゴは、アセルブラリアという四放サンゴの仲間で、およそ4億2500万年前(古生代シルル紀)に生きていました。このサンゴは、北欧のバルト海に浮かぶスウェーデン領ゴトランド島で採集された標本で、4億年以上たった現在でも、サンゴ骨格の表面が生きていた当時そのままに保存されている珍しい例です。
今ゴトランド島があるバルト海は、水温も塩分濃度も低く、サンゴ礁ができるような環境にありませんが、シルル紀の頃は熱帯にあって、400キロメートルに及ぶ礁が発達していました。アセルブラリアはその当時を代表する造礁生物の1つです。
(総合学術博物館長 森 啓)

